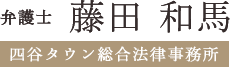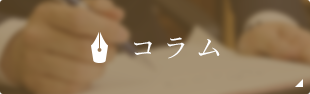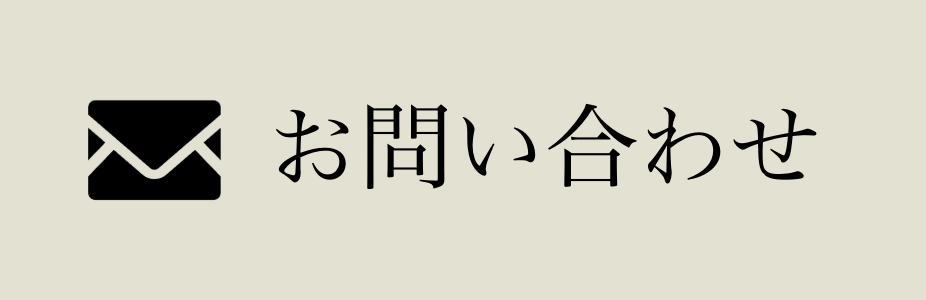自己破産による6つのデメリット!四谷の現役弁護士が詳しく解説

自己破産は,多額の借金を返済できなくなった際に裁判所を通じて免責を受ける手続きです。
借金の支払い義務がなくなる一方で,財産の処分や信用情報への影響など,いくつかのデメリットも伴います。
本記事では,自己破産の仕組みや注意点,具体的なデメリットについて詳しく解説します。
◼︎目次
1. 自己破産とは?【四谷の弁護士が解説】
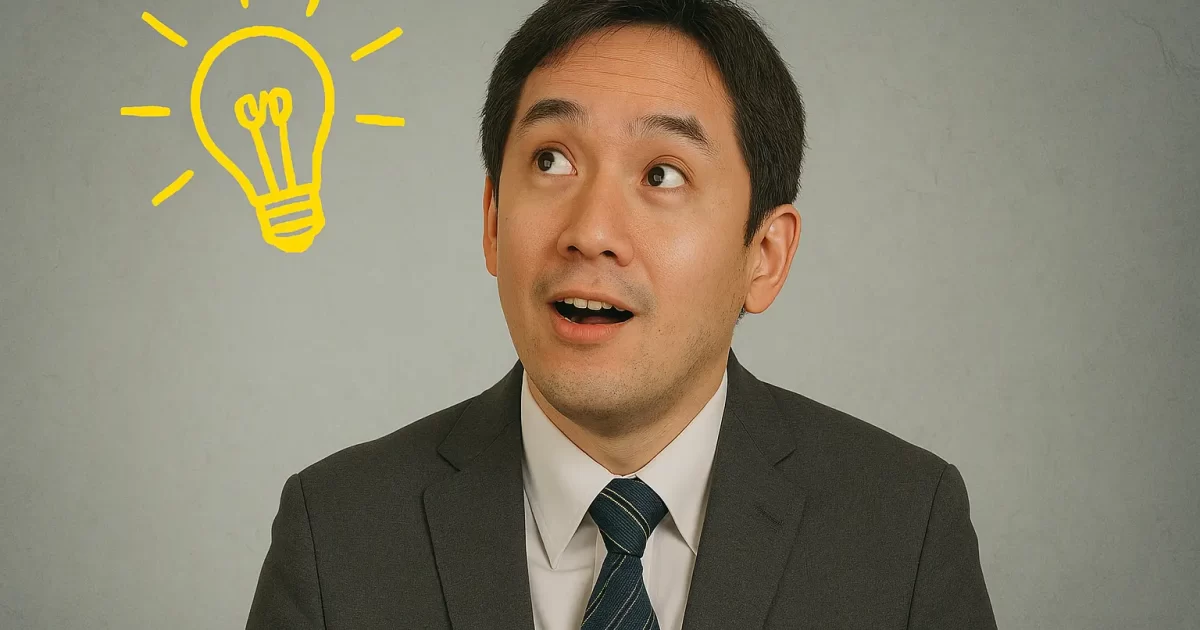
自己破産とは,多額の借金を抱え,現在の収入や財産の処分では債務の返済が困難な場合に,裁判所に申立てを行い,支払い義務を免除してもらう手続きのことです。
借金の支払い義務がなくなる仕組み
裁判所による「免責許可決定」が出た場合,ほとんどの借金が帳消しになります。
ただし,次のようなケースでは免責が認められない場合もあります。
(1)債務が非免責債権に該当する場合(破産法253条1項各号)
免責許可決定の対象外となる債権が存在します。
- 税金や保険料などの公租公課
- 養育費や婚姻費用
- 罰金等の請求権
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
などです。
(2)免責不許可事由がある場合(破産法252条1項各号)
免責許可決定が不許可とされる場合があります。
- ギャンブル,投資,浪費による借金の場合
- 前回の破産による免責許可決定後7年以内の場合
- 不当に財産を減少させたり,債務を負担し,債権者を不平等に扱った場合
- 相手方を騙して借金をした場合
- 裁判所(管財人を含む)に虚偽の書類等を提出した場合
などです。
ただし,ギャンブル,投資,浪費による借金の場合や前回の破産による免責許可決定後7年以内の場合には,免責不許可事由に該当しても,適切に破産申立を行うことで,裁量免責により免責許可決定となるケースは多いです。
自己破産手続の種類
自己破産の手続きには,借金に至る経緯や財産状況に応じて 「同時廃止手続」と「管財手続」の2種類があります。
管財人が選任されるか否かで手続の内容が異なります。管財人が選任される場合は,裁判所に最低20万円の引継予納金の準備が必要になり,免責許可を得るために管財人の業務に協力する必要があります。
(1)同時廃止手続
換価可能な資産が明らかになく,借入の経緯等についても免責不許可事由に該当しないことが明らかな場合に,裁判所に破産管財人が選任されることなく,破産手続が終了する手続です。その後,免責審尋手続のために裁判所には出廷します。
東京地方裁判所の場合には,申立時に弁護士と裁判官が面談し(即日面接制度といいます),同時廃止手続と決定されると,ご本人様は,免責審尋手続のために裁判所に多くの場合は1回出廷することで手続が終了するため,手続が簡易化されています。
(2)管財手続(管財事件)
管財手続は,少額管財事件と一定規模以上の大規模管財(特定管財)事件に分かれます。
管財事件のほとんどは少額管財事件ですので,ここでは少額管財事件を管財事件として説明します。
管財事件では,同時廃止手続と異なり,裁判所により破産管財人が選任されます。20万円以上の換価可能性がある資産や免責不許可事由の存在が疑われるような場合等に管財事件となります。
東京地方裁判所の場合には,申立時に弁護士と裁判官が面談し,管財手続と決定されると,ご本人様は,管財人と面接し,破産手続と免責審尋手続のため裁判所に出廷することが必要となります。
管財人は資産の有無の調査・資産の換価,免責不許可事由の有無,裁量免責を行ってよいか等の調査を行います。
2. 新宿四谷の弁護士が教える自己破産のデメリット【6選】
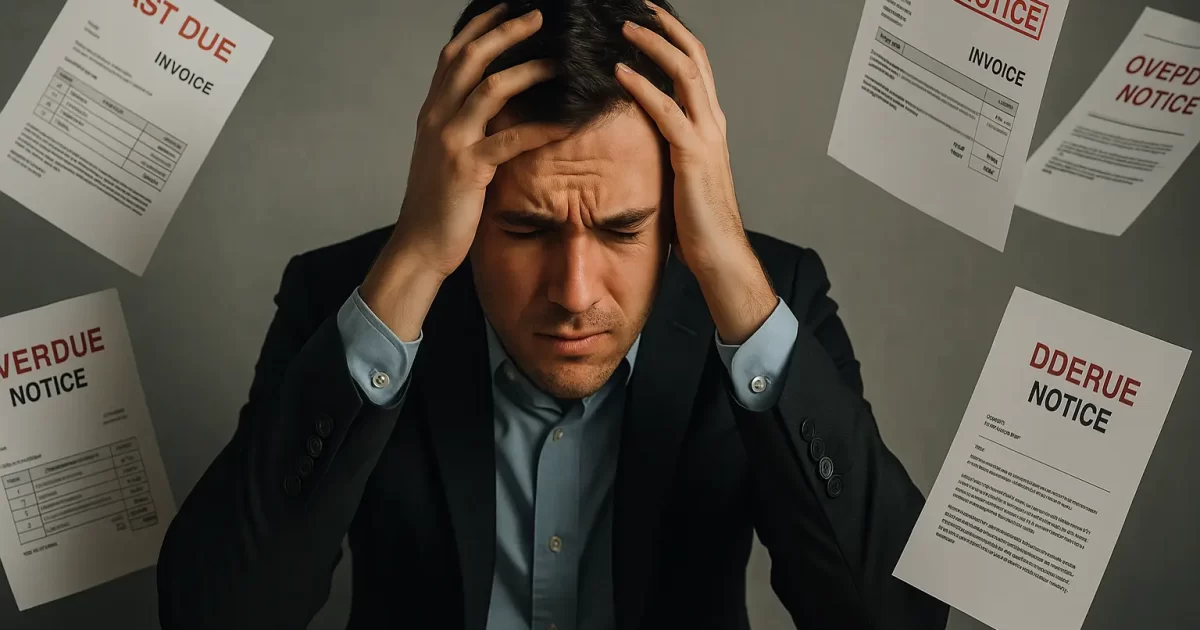
自己破産をすると,借金が帳消しになるメリットがある一方で,いくつかのデメリットも伴います。主なデメリットを詳しく見ていきましょう。
1. 数年間,新たな借り入れができない
自己破産をすると, 信用情報機関に「事故情報」として登録 されます(いわゆる「ブラックリスト」入り)。
ただし,信用情報機関への「事故情報」の登録は,任意整理の場合や個人再生の場合も同様であり,自己破産特有のデメリットではありません。
その結果,以下のような影響が出ます。
・ クレジットカードの作成ができない
・ 住宅ローンや自動車ローンの審査に通らない
・ 保証人の審査に通らない
などです。
ただし,これは永遠に続くわけではなく,免責許可決定を得てから約5〜7年で信用情報が回復します。
2. 価値のある財産が処分される
破産手続開始後は,自由財産を除き,全て換価(処分)されるのが原則になります。
そのため,自宅やローン完済済の自動車は換価されることになり,失うことになります。
自由財産は,99万円以下の現金,生活必需品や相当額の給与債権等の差押禁止財産になります。破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)も原則として換価処分の対象外になります。
また,東京地方裁判所では,合算して20万円以下の預貯金残高,合算して解約返礼金20万円以下の保険等は当然自由財産として,手続なく自由財産扱いとなります。
さらに,破産管財人が換価不能な財産と判断し,財産放棄した場合には,自由財産になります。例えば,ローン完済済の自動車ではあるものの,初年度登録から10年以上経過している国産自動車や自動二輪車のような場合には,財団から放棄されることも少なくありません。
それ以外の場合には,自由財産の拡張の申立を行うことで,例外的に自由財産として認められることはあります。
例えば,保険の解約返戻金合計額20万円以上の場合,個々の解約返戻金額を考慮せずに保険契約全てが換価対象となりますので,その一部又は全部につき自由財産の拡張の申立を行い,自由財産として認めてもらうように活動します。
3. 家族等にバレる可能性がある
自己破産は,自己破産すると,政府が発行する 「官報」 に氏名・住所などの情報が掲載されます。
もっとも,一般的には,官報は,金融機関・貸金業者等がチェックするのみで,一般の人がチェックすることはほとんどないとされているため,基本的に家族等に知られずに手続きを進めることも可能とされていることが多いです。
ただし,次のようなケースでは家族等に知られることになります。
少なくとも同居親族には破産をすることを説明はしておいた方が良いケースは多いです。
また,下記のような事情で特定の債権者を除外して債務整理をする場合は,任意整理によらざるをえません。
- 保証人が存在する場合には,保証人に対して債権者から請求がいく等の経緯から,親族等の保証人に対して破産することが知られます。
- 親族・知人や勤務先からの借入がある場合には,破産手続や個人再生手続では等しく債権者と取り扱う必要があることから,破産を行う場合にはその旨を伝える必要があります。
- 自宅,車や保険等を一定の財産処分をする場合には,財産処分に至る経緯から親族等の保証人に対して破産することが知られます。
- 5年以上勤務しているような場合には退職金が存在するか否か,その額に関して資料を提出する必要がある場合があります。この場合,退職金について確認が容易な勤務先の場合には問題ありませんが,勤務先に資料を作成したいていただく必要がある場合には事情を説明せざるをえないケースもあります。
- 特定の銀行から借り入れがあり,勤務先から特定の銀行の口座へ給与を支払う指定があるような場合には,給与の振込先の変更を求めるために,勤務先に破産予定である等の事情を説明せざるをえないケースもあります。
- 家族に破産者名義で家族カードを利用させている場合には,家族が使用中のカードも使用できなくなるため,親族等に破産することが知られる可能性があります。
- クレジットカードで公共料金等を支払っていた場合には,カードでの支払ができなくなるため,同居親族に破産することが知られる可能性があります。
- 破産手続中に管財人から同居親族の収入や貯金等について資料として提出を求められるケールもありますので,この場合には,同居親族に破産することが知られる可能性があります。
などです。
4. 保証人に迷惑がかかる
破産者の債務と保証人の債務は別債務になるため,破産をしても保証人の債務は免除されません。
保証人は支払義務があり,破産をした場合,債権者から保証人に対して請求されることになります。
債権者から保証人に対して速やかに請求されないこともあり,保証人への請求時点で元本債務以外に遅延損害金が発生しているケースもあります。
そのため,事前に保証人へ説明・謝罪することが重要ですし,保証人から債権者に連絡をし,分割払の申出をする等対応する必要があるケースもあります。
なお,保証人に迷惑を掛けれないものの,債務整理をする必要がある場合には,その保証債務つき債務のみ除外して,他の債務について任意整理する方法によるしかありません。
5. 一部の職業・資格が制限される
自己破産により,特定の職業や資格が一定期間(復権するまで)制限されます。
以下の資格業については制限があります。
- 弁護士,税理士,公認会計士,司法書士,社会保険労務士,行政書士など
- 建築士,不動産鑑定士,宅地建物取引士,土地家屋調査士など
以下の他人の財産を扱う職業に制限があります。
- 貸金業者,質屋,生命保険募集人など
以下のような職業にも制限があります。
- 旅行業務取扱管理者,警備員など
になります。
6. 二度目の破産が認められにくくなる
自己破産をすると,7年以内の再度の破産申立は免責不許可事由に該当します。
そのため,裁量免責されない限りは,再度の破産申立を行っても,債務が免責(帳消し)にはならず,通常のケースより免責されにくくなります。
また,7年以上経過しても,管財手続になり,免責不許可事由の有無の判断の調査や裁量免責の判断は慎重になります。
3. まとめ

自己破産には 「借金を帳消しにできる」 という大きなメリットがある一方で, 「財産の処分」「信用情報への影響」「保証人への影響」 などのデメリットもあります。
自己破産を検討する際は,他の債務整理方法(任意整理・個人再生)と比較しながら,最適な手続きを選ぶことが大切です。
「自己破産をすべきか迷っている…」
「家を残したまま借金を整理したい…」
そんな方は,一度 専門の弁護士に相談することをおすすめします!
四谷の弁護士藤田は金融機関からの借入の債務整理のご相談に限り初回相談無料です。まずはお気軽にご相談ください。

監修:弁護士藤田和馬
四谷タウン総合法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(第一東京弁護士会所属)
様々な法律相談に関する相談実績年間200件以上です。
何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。