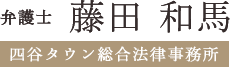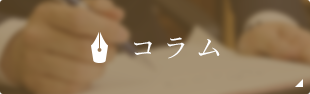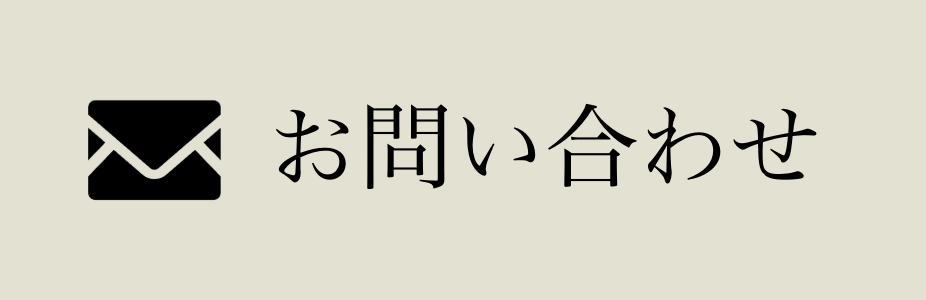【急いで!】相続放棄には期限があります|親の借金に気づいたあなたへ
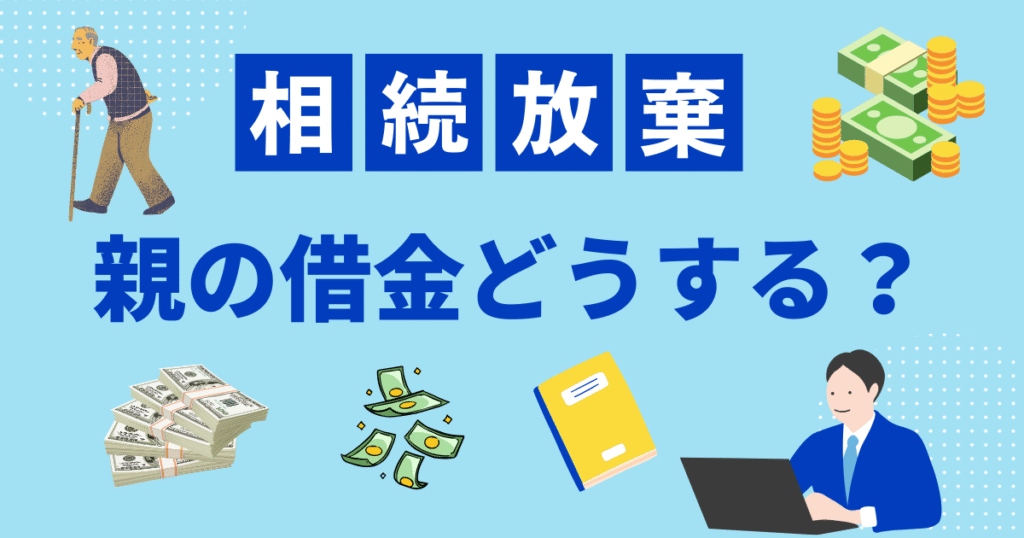
「親が亡くなって、気持ちの整理もまだつかない。
でも、そろそろ相続のことも考えないといけない…」
そんな中で、通帳や請求書を見ていると「どうやら借金があるらしい」と気づき、慌てて調べ始めた方も多いのではないでしょうか。特に最近、「相続放棄には期限がある」という情報を目にして、不安になった方もいらっしゃるかもしれません。
✅ 「もう親の死亡から3ヶ月近く経ってしまったけど、まだ間に合うのか?」
✅ 「放棄すれば借金を背負わずに済むって聞いたけど、本当にできるの?」
✅ 「自分で手続きするのは不安。弁護士に頼むべきなのか…?」
相続放棄には原則として、「相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」という期間制限ルールがあります(民法915条1項)。
ですが実際には、「いつから数えるのか」「例外があるのか」など、ケースによって判断が異なることも多く、自己判断で放置すると大きな損失につながる可能性もあります。
本記事では、相続放棄の期限に関する基礎知識をはじめ、
✅ 被相続人が死亡してから3ヶ月経過した場合にまだ相続放棄が可能なケース
✅ 弁護士に相談するメリットや流れ
などを、わかりやすくご紹介します。「もしかして、もう間に合わないかも…」と悩んでいる方ほど、ぜひ最後まで読んでみてください。まだ間に合う可能性はあります。ひとりで抱え込まず、まずは正しい情報を知ることが大切です。
◼︎目次
1. 相続放棄には「3ヶ月の期限」があるって本当?

「相続放棄には3ヶ月の期限があります」
そう聞くと、「自分はもう手遅れかもしれない」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
たしかに、相続放棄には明確な期限が存在します。ですがこの“3ヶ月ルール”は、一見シンプルに見えて、実際のカウント開始時期や例外も存在し、誤解されているケースが非常に多いのです。
まずは、相続放棄に関する基本的なルールと、「熟慮期間」と呼ばれる3ヶ月のカウント方法について、わかりやすく解説していきます。
相続放棄の基本ルールと「熟慮期間」とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金などを一切引き継がないと宣言する法的手続きです。
遺産のなかに借金や保証債務などのマイナス財産があるときに、相続人がこれを回避するために行います。
この相続放棄には、民法で定められた明確な期限があります。
それが、いわゆる「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれるルールです。
📌 熟慮期間とは?
民法915条では、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に、相続放棄または承認の意思表示をしなければならないと定めています。
つまり、相続人はこの3ヶ月の間に、
- 相続するか(単純承認)
- 相続をやめるか(相続放棄)
- 借金や資産を精査して一部責任を限定する(限定承認)
を選ぶ必要があるのです。
この3ヶ月の間に相続放棄の申述を家庭裁判所に提出しないと、原則としてすべてを相続したものとみなされる(単純承認)ため(民法921条2号)、借金の返済義務も生じてしまいます。
したがって、債務がある場合に「放っておく」という選択は最も危険であり、何らかの判断を3ヶ月以内に行う必要があるのです。
「親が亡くなった日から3ヶ月」ではないケースもある
相続放棄には「3ヶ月以内」という期限がありますが、必ずしも「死亡日=起算点」とは限りません。
民法では「自己のために相続の開始があったことを知ったときから」と規定されており、この“知ったとき”とは、被相続人の死亡の事実に加えて、それによって自己が相続人となったことを覚知することが必要と解釈されています。そして、相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたために、相続放棄の申述をしないまま熟慮期間を徒過した場合、このように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識可能な時から熟慮期間を例外的に起算することができるとされています。
ケースによって解釈は異なりますが、次のようなケースでは相続放棄することが考えられます。
たとえば、次のようなケースでは「親が亡くなった日」よりも後に起算される可能性があります:
- 被相続人と疎遠で、死亡を知らなかった
- 相続人であることを後になって知った
- 第1順位の相続人(配偶者や子)が相続放棄したことを後になって知った他の相続人
- 親族や行政からの連絡がなく、戸籍を調べて初めて知った
このような場合、相続放棄の「3ヶ月カウント」は、死亡日ではなく“相続が発生したことを自分で認識した日”からスタートする可能性があります。
✅ 重要なのは、相続人が被相続人の死亡を知ることができなかった理由等の客観的事実を整理して説明する書面(事情説明書)を裁判所に提出することです。
「借金を知った日」が起算点になることもある
もうひとつ重要なポイントは、判例は、相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じていたために、相続放棄の申述をしないまま熟慮期間を徒過した場合、このように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常これを認識可能な時から熟慮期間を例外的に起算することができるとされています。簡単にいえば、「借金の存在を知った日」が起算点と判断されることもあるという点です。
親の死後、しばらく経ってから遺品整理や郵便物の確認を通じて借金が発覚する――このようなケースは珍しくありません。
実際、次のような状況では「借金の存在を知った日」が起算点になりうるとされています:
- 死亡時には借金の存在がわからなかった
- 相続財産がプラスだと思っていたが、後から債務が出てきた
- 債権者からの通知で初めて知った(カードローン、医療費、保証債務など)
こうした場合、「親が亡くなったこと」自体は知っていたとしても、借金の存在=相続放棄すべき理由を知った日を起算点として主張できる可能性があります。
ただし、この主張を通すためには、借金の存在を知った日を証明する証拠や、気づくまでの経緯の説明が求められます。
✅ 例えば、請求書の封筒や郵送物の開封日、受け取った連絡の記録などが重要になります。
こうした事情の整理や説明文の作成は、弁護士が得意とする分野です。「もうダメかも」と思う前に、まずは相談することで道が開けることも多いです。
2. 相続放棄の期限が過ぎたらどうなる?
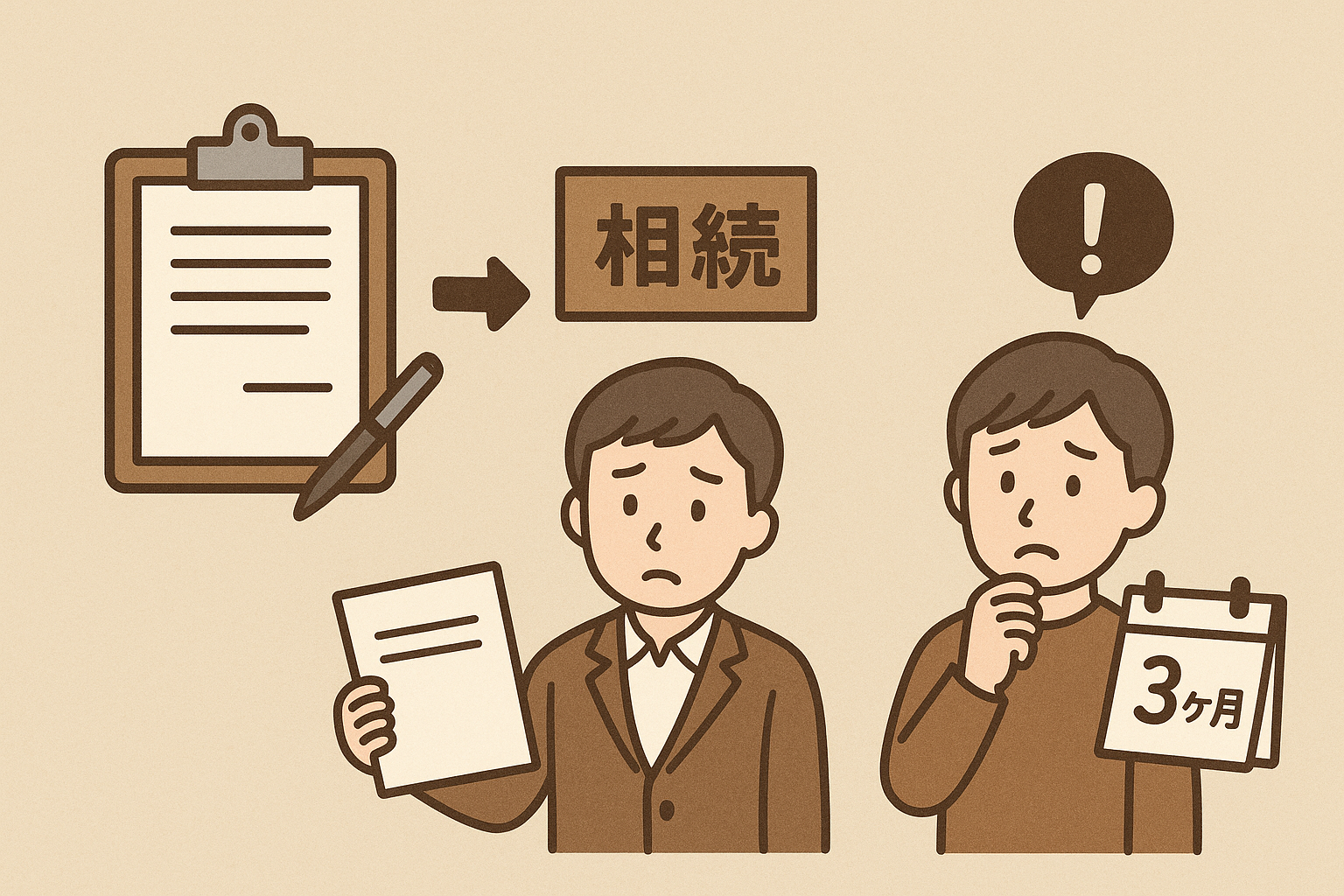
「相続放棄には3ヶ月の期限があるらしい」
そんな情報を見て、急に不安になった方も多いのではないでしょうか。
親が亡くなり、気持ちの整理もつかないまま手続きに追われていたところに、借金の存在が発覚した――。
「相続放棄すれば借金は引き継がなくて済む」と聞いたものの、時間ばかりが過ぎてしまい、“もう間に合わないのではないか”と焦りを感じている方は少なくありません。
実はこの“3ヶ月ルール”には、よく誤解されがちな点がいくつかあります。
この記事では、相続放棄の期限に関する基本的なルールや、「いつからカウントが始まるのか」「期限が過ぎたらどうなるのか」といった疑問に、わかりやすくお答えしていきます。
原則は「単純承認」=借金を引き継いでしまう
相続放棄の期限である「3ヶ月」を過ぎてしまった場合、法律上は「単純承認(たんじゅんしょうにん)」とみなされ、被相続人の財産も借金もすべてを無条件で引き継いだ状態になります。
単純承認とは、「相続人として相続を受け入れた」とされる状態のことです。
財産にプラスがあれば得になりますが、借金のほうが多ければ、それをすべて負担しなければならないというリスクがあります。
また、期限内であっても以下のような「相続人が相続財産の全部又は一部を処分した」と評価される行動(民法921条1号)をとると、単純承認したとみなされる可能性があるため注意が必要です:
- 相続財産を売却・処分してしまった
- 預貯金を引き出した
✅ これらの行為は、裁判所から単純承認があったと判断されることがあります。
「何もしなければ相続しない」という誤解は非常に危険です。
相続を放棄したいのであれば、家庭裁判所への手続きが必要不可欠です。
例外的に相続放棄が認められるケース
とはいえ、死亡してから3ヶ月の期限を過ぎてしまったからといって、すべてのケースで相続放棄が絶対に認められないわけではありません。
実務では、次のような的事情がある場合、相続放棄が受理されるケースがあります。
✅ 相続放棄が認められる主なケース
- 親が亡くなったことをすぐに知らなかった
- 自分が相続人だと後から判明した(再婚・異母兄弟など)
- 財産はプラスだと思っていたが、後になって借金が判明した
このようなケースでは、「なぜ3ヶ月を過ぎたのか」「放棄する意思がなかったのか」などについて、事情説明書を提出し、合理的な理由があれば裁判所が受け入れてくれる可能性があります。
✅ 弁護士に相談すれば、受理される可能性があるかどうかを具体的に判断し、必要書類の作成・主張立証まで一貫してサポートが可能です。
3. 期限ギリギリでも相続放棄に間に合う可能性はある?
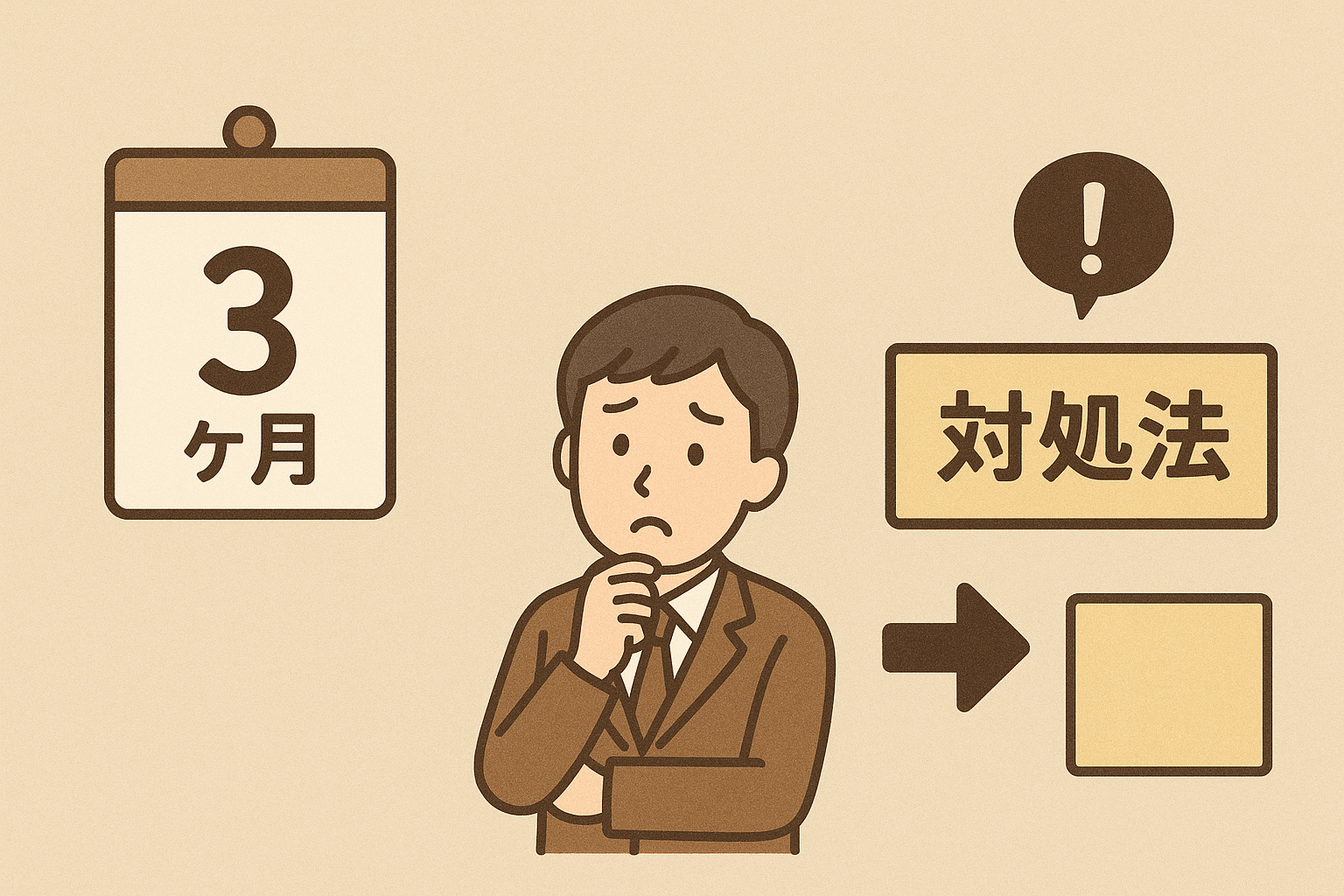
「もうすぐ3ヶ月が経ってしまう…」
「今日がちょうど3ヶ月目かもしれないけど、まだ間に合うの?」
相続放棄の相談で多いのが、こうした**“ギリギリのタイミング”でのご連絡**です。
精神的にも時間的にも追い詰められた状況の中、「自分でできるのか」「何から始めるべきか」が分からず、不安ばかりが募ってしまう方も少なくありません。
ですが、結論から言えば――まだ間に合う可能性はあります。
実際、期限当日にご相談いただき、必要な添付書類が準備済みの場合には即日で書類を作成・提出できた事例もありますし、「本当にダメかも…」と思っていた方が救われたケースもあります。また、一定の場合には熟慮期間の伸張も認められています(民法915条1項ただし書)
ここでは、期限ギリギリのタイミングでも相続放棄が成立する可能性と、今すぐ取るべき行動について、わかりやすく解説していきます。
まずは「家庭裁判所への申述書提出」を急ごう
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、受理されてはじめて成立します。
つまり、「放棄したいと思っている」だけ、他の相続人に相続放棄した旨の意思表示をしただけでは、何も手続きしたことにはなりません。
期限内(=起算日から3ヶ月以内)に、申述書を裁判所へ提出していることが必要です。郵送でもかまいません。
家庭裁判所は「消印日」ではなく、「裁判所に到達した日」を基準に判断します。
そのため、ギリギリでの郵送はリスクもあるため、普通郵便による郵送ではなく追跡可能なレターパックでの郵送や家庭裁判所への持参が推奨されます。
弁護士が入ることで書類不備や認定争いを回避できる
相続放棄の申述書は、記入項目が多く、戸籍や住民票などの添付書類も必要です。
書類の不備があった場合、裁判所から補正の連絡が来て、期限内に補正が間に合わず「不受理」とされてしまう可能性があります。
また、放棄の起算点が「死亡日ではない」「借金を後から知った」と主張するケースでは、客観的な証拠や事情説明書の添付が極めて重要です。
✅ 弁護士に依頼すれば:
- 状況に応じた適切な起算点の主張
- 裁判所に納得してもらえる書面作成
- 必要書類の収集や早期の提出
などをプロの視点でサポートできるため、ギリギリでも失敗リスクを最小限に抑えることができます。
相続放棄の申述書は、記入項目が多く、戸籍や住民票などの添付書類も必要です。
書類の不備があった場合、裁判所から補正の連絡が来て、期限内に補正が間に合わず「不受理」とされてしまう可能性があります。
また、放棄の起算点が「死亡日ではない」「借金を後から知った」と主張するケースでは、客観的な証拠や事情説明書の添付が極めて重要です。
✅ 弁護士に依頼すれば:
- 状況に応じた適切な起算点の主張
- 裁判所に納得してもらえる書面作成
- 必要書類の収集や早期の提出
などをプロの視点でサポートできるため、ギリギリでも失敗リスクを最小限に抑えることができます。
「間に合わないかも…」と思った時にすべき行動
「もしかして、もう間に合わないかもしれない」
そんな不安があると、どうしても思考が止まってしまい、動けなくなる方も少なくありません。しかし、諦めるのはまだ早いです。
以下の行動を、できれば今すぐに行ってください。
✅ 行動①:相続放棄の起算点を思い出し、整理する
「亡くなったことを知った日」「借金の存在を知った日」など、起算点になりそうな日付を確認。また、その裏付けとなる客観的な資料の準備をする。
どこから数えるかによって、まだ間に合う可能性があることも
✅ 行動②:できるだけ早く弁護士に相談・依頼する
期限内の可否判断・書類の作成・早期提出のサポートが可能です。
一人で悩むより、専門家の判断で「間に合う道」が開けることもあります。相続放棄をする方の現在戸籍謄本を取得いただくとその後のサポ-トがスムーズになることが多いです。
✅ 今この瞬間が、相続放棄を成功させるかどうかの“分かれ道”です。
「間に合わないかも」と思っても、動けば助かる可能性が十分にあります。
4. 相続放棄の手続きの流れと必要書類
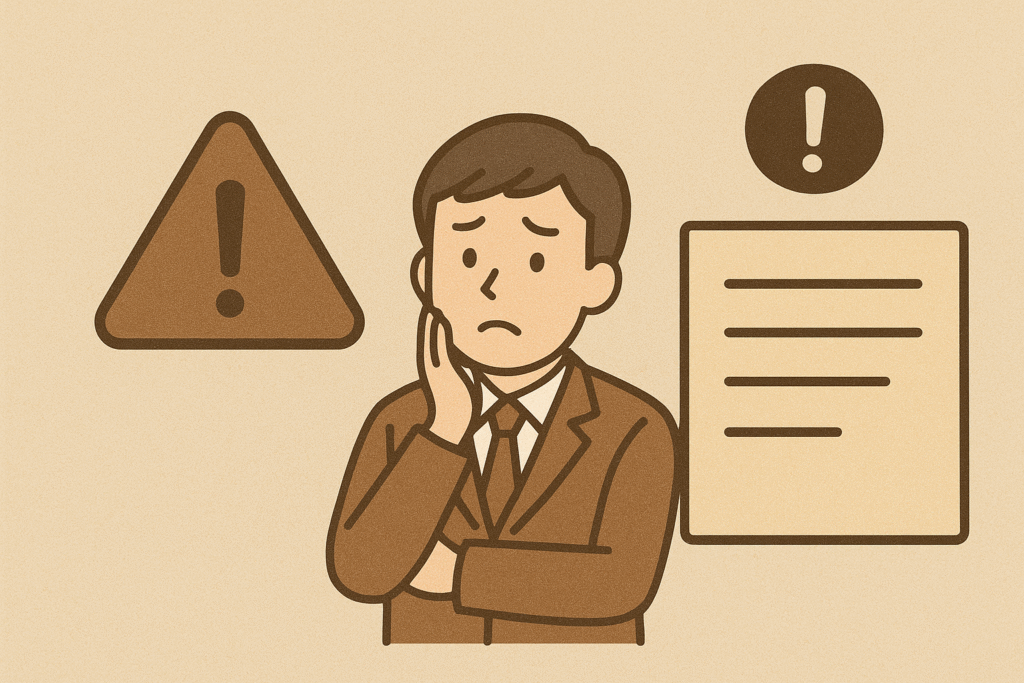
「相続放棄したい気持ちはあるけれど、実際に何をすればいいのか分からない…」
そんな不安を抱えたまま、時間だけが過ぎてしまう方は少なくありません。
相続放棄は、家庭裁判所に対して正式な書類を提出する必要があり、書き方や添付書類に不備があると受理されない可能性もあるため、慎重な対応が求められます。
ですが、流れを一度把握してしまえば、必要な準備や注意点はそれほど難しくありません。
この章では、相続放棄の基本的な流れと、申述書の提出方法、必要書類、そしてよくある不備のポイントについて、実務経験をもとにわかりやすく解説していきます。
家庭裁判所への提出方法(持参・郵送どちらもOK)
相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の「最後の住所地」を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することで手続きが始まります。家庭裁判所であればどこでもいいわけではなく、相続人最寄りの住所地を管轄する家庭裁判所とは限らないのでご注意ください。
提出方法は、以下の2つから選ぶことができます。
① 直接持参して提出する
② 郵送で提出する
✅ それぞれの方法には以下のような特徴があります:
| 方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 持参 | 即日で提出・受理確認ができる | 原則として平日昼間の開庁時間内のみ対応 |
| 郵送 | 遠方でも提出可能。忙しい方に便利 | 到達日が提出日になるため、期限ギリギリは要注意 |
特に申述期限が迫っている場合は、必ず速達やレターパックプラスなど追跡可能な方法で送付し、到達日時を証明できるようにしておくことが重要です。
不安な場合は、到着したか否か家庭裁判所に電話で確認をとると安心です。
申述書・戸籍・事情説明書など準備すべきもの
相続放棄の申述に必要な書類は、ケースによって多少異なりますが、一般的には以下の書類を準備します:
✅ 相続放棄に必要な基本書類
| 書類名 | 内容 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 家庭裁判所所定のフォーマット。 |
| 被相続人の住民票除票又は戸籍附票 | 被相続人の最終住所を確認するために使用 |
| 申述人(あなた)の戸籍謄本 | 相続人であることを確認するために必要 |
| 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 *親・兄弟等が相続人になる場合には被相続人の出生から死亡するまでの戸籍が必要になります。 | 相続関係を証明するために必要 |
| 事情説明書(必要な場合) | 期限を過ぎた申述や特殊事情がある場合に添付 |
特に戸籍については、被相続人の出生から死亡までのつながりが分かるすべての戸籍を揃える必要がある場合は、予想以上に時間がかかることも。不備や取り寄せ漏れを防ぐため、弁護士に依頼する方も多いポイントです。
不備があると受理されない!チェックポイント一覧
相続放棄は、「提出すれば終わり」ではありません。
書類に不備があると、家庭裁判所から補正を求められ、期限内に補正が間に合わないと不受理となってしまう可能性もあります。
✅ 以下のような点は、特に注意が必要です:
- 相続放棄申述書の記載漏れ
- 戸籍の一部が抜けており、出生から死亡までがつながらない
- 裁判所の管轄が間違っている(例:申述人の住所地ではなく、被相続人の住所地が基準)
- 「事情説明書」が必要なのに添付していない、説明が不十分
特に、期限が迫っている場合に不備があると、再提出の時間がなくなってしまうこともあるため、慎重なチェックが求められます。
✅ 弁護士に依頼すれば、こうした不備のチェックや補正リスクの排除、適切な裁判所への提出までを一括して任せられるため安心です。
時間的余裕がないときほど、専門家のサポートが重要になります。
5. 相続放棄を弁護士に相談するメリット

「できることなら自分で手続きしたいけど、時間もないしミスが怖い…」
相続放棄のご相談では、こうしたお悩みを抱える方が非常に多くいらっしゃいます。
特に期限ギリギリのタイミングでは、書類の記載ミスや必要書類の不備が命取りになりかねません。
弁護士に相談・依頼することで、そうしたリスクを回避しながら、的確かつスピーディに相続放棄の手続きを進めることが可能になります。
この章では、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットや、実際の費用・相談の流れなどをわかりやすくご紹介します。
「相談すべきか迷っている」という方こそ、ぜひ参考にしてください。
期限ギリギリでも即日書類作成・提出が可能
相続放棄の期限が差し迫っている場合、スピードが何よりも重要になります。
弁護士に依頼すれば、状況をヒアリングしたその日のうちに、必要書類の作成・提出までを一括対応できる場合もあります。
✅ 実際に当事務所でも以下のようなご相談が多くあります:
- 「今日でちょうど親が死亡してから3ヶ月です。間に合いますか?」
- 「明日が期限ですが、どうしても放棄したいです」
こうしたご相談に対して、弁護士が申述書や事情説明書を即日作成し、裁判所への速達対応や持参提出により、期限内に間に合わせたケースはあります。
自分一人では対応しきれない状況でも、弁護士ならその日のうちに最善の方法を提案・実行できるという点は大きな安心材料です。
戸籍収集や書類作成の負担をすべて任せられる
相続放棄では、被相続人の「出生から死亡までの戸籍謄本」や、申述人の戸籍、住民票、場合によっては事情説明書など、多くの書類を揃える必要があります。
これらをご自身で集めて、内容を理解し、正しく書類を整えるのは想像以上に手間がかかります。
✅ 弁護士に依頼すれば、以下の作業をすべて任せることができます:
- 必要書類のリストアップ
- 戸籍等必要資料の収集
- 相続関係の整理と相続人の特定
- 裁判所に提出する書類一式の作成・確認
- 書類提出後の補正対応や連絡調整
ご自身では不安な点や分からないことが多くても、すべてを任せることで安心して進められるのが大きなメリットです。
特に本業や家庭が忙しい方にとっては、「任せられる」こと自体が大きな価値になります。
相談の流れと依頼後の動き
相続放棄は、家庭裁判所への正式な申述手続きが必要な“法律行為”です。
そのため、「どう進めればいいのか分からない」「何から始めればいいのか不安」と感じる方が多いのも当然です。
ここでは、当事務所に相続放棄をご相談いただいた場合のご相談から完了までの基本的な流れをご紹介します。
ご相談から受理決定までの流れ(例)
- 【お問い合わせ】
電話・メール等から、お気軽にご連絡いただけます。 - 【状況のヒアリング】
被相続人の死亡日、相続人の関係性、借金の存在を知った経緯、申述期限などを丁寧に確認します。 - 【必要書類の案内と準備】
相続放棄に必要な戸籍や住民票、申述書などの必要書類を整理、収集・作成をすることも可能です。 - 【家庭裁判所への申述】
弁護士が申述書等を作成し、速やかに管轄の家庭裁判所に提出します(速達・持参対応も可能)。 - 【裁判所からの通知対応】
申述内容に関する補足説明が求められた場合や、追加資料の提出依頼があった場合も、弁護士が対応を代行します。 - 【受理決定・完了のご報告】
裁判所からの受理通知が届き次第、正式に手続き完了となります。また、債権者に資料として提出するため「相続放棄申述受理証明書」を取得します。
相続放棄は「自分で何とかしよう」と思っても、期限や書類の不備などでトラブルに発展しやすい手続きです。
弁護士に任せることで、複雑な手続きを安心して進められますし、ご本人のご負担を最小限に抑えることができます。
「どのタイミングで相談すべきか分からない」という方も、まずはお気軽にご連絡ください。
状況をお伺いした上で、今できる最善の方法をご提案いたします。
6. まとめ|「もう遅いかも」と思っても、今すぐ相談を

相続放棄には「3ヶ月の期限」があるというルールは確かに存在します。
しかし、この記事でご紹介してきたように、そのカウントの起点や例外的な事情によって、相続人が死亡してから3ヶ月経過後でも放棄が認められるケースも少なくありません。
✅ 「もう間に合わないかも…」と思っていても、
起算点の時期によって期限内と扱われるケース裁判所に事情説明書を提出し、例外的に受理された事例弁護士が即日で対応して期限当日に提出できた実例
など、行動次第で救われる可能性があるのが相続放棄の実務です。
とくに、相続財産に借金が含まれている場合、何もせずに放置してしまうと、知らないうちに借金を引き継ぐことになりかねません。
「自分は相続放棄したつもりだった」という思い込みが、取り返しのつかない事態に繋がることもあります。
✅ 少しでも不安を感じたら、まずは一度ご相談ください。
弁護士があなたの状況を丁寧にヒアリングし、今からできる最善の選択肢をご提案いたします。
相続放棄はスピードが命。一人で抱え込まず、専門家と一緒に、後悔のない判断をしていきましょう。

監修:弁護士藤田和馬
四谷タウン総合法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(第一東京弁護士会所属)
様々な法律相談に関する相談実績年間200件以上です。
何かお困りのことがあればお気軽にご相談ください。